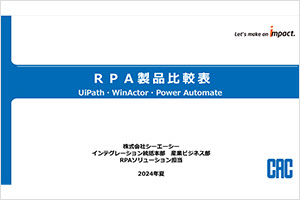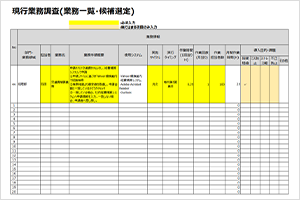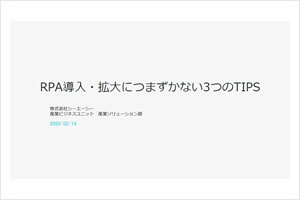RPAは扱いづらい? 理由とその解決策|複雑化・野良ロボットを防ぐ方法 〜 放置されたロボットが現場を混乱させないために。いま必要な見直しと改善のヒント〜
目次
はじめに
RPAの導入が広がるなかで、便利なはずのRPAが「現場の混乱を招く“悩みのタネ”になっている」
――そんな声を耳にすることが増えてきました。
その“悩みのタネ”となってしまう原因として”野良ロボット”や”複雑化したロボット”が挙げられます。
具体的には、
「作った人しか分からない“ブラックボックス化”したロボット」
「存在しているだけで、使われているかすら分からないロボット」
「処理の内容が複雑すぎて、どのような処理をしているのか解読できず放置されるロボット」
といったものです。
“野良ロボット”や”複雑化したロボット”は、RPAが定着し始めた企業ほど発生しやすい課題です。その課題に直面することにより、RPAは「扱いづらい」「難しい」と認識されてしまうことがあります。
本記事では、実際に生じている現場の課題を整理し、読者の皆様にとって業務課題改善に直結し、今すぐ確認できる見直しの観点や改善のポイントをご紹介します。
最後までご覧いただけますと幸いです。
RPAが「扱いづらい」と言われる理由
状況によって様々ですが、主に下記のような要因はロボットを複雑化したり、管理されない野良ロボットの増加を招きやすく、結果としてRPAは「扱いづらい」と感じさせる状態を引き起こします。
開発における属人化
ロボットの設計や仕組みを一部の担当者のみが理解している状態です。その担当者が不在になると修正や保守が滞り、他のメンバーが対応できなくなるリスクを抱えています。
引き継ぎ不足
マニュアルやナレッジの共有が不十分な場合、ロボットの役割や処理内容が組織内で正確に伝わらず、「何を行っているロボットなのか把握できない」という状況が生じやすくなります。
小さな修正の積み重ね
部分的な改修や追加対応を繰り返すことで、処理構造が徐々に複雑化し、全体像が把握し辛いロボットとなってしまいます。結果として、改修や運用の難易度が高まります。
管理体制がととのっていない
ロボットの管理ルールやガイドラインが整備されていないため、部署や担当者ごとに運用の手法や手順がまちまちな状態になることで組織全体の統制が損なわれ、監査や障害対応に支障をきたします。たとえば、ロボットの棚卸しやメンテナンスが行き届かず、「どこに、どんなロボットが存在しているのか分からない」という状況が発生しやすくなってしまいます。
一度このような状況に陥ると、せっかく導入したRPAを活用しきれずに、逆に業務のボトルネックになってしまう可能性もあります。
野良ロボットを生まないための基本的なポイント
上記のような事態を防ぐためのポイントと具体例を、「開発時」「リリース時」「運用」それぞれのフェーズでお伝えします。
※弊社では計画、開発、運用、展開のガイドラインを定めていますが、ここではすぐ実施できる観点に絞って簡易化した内容を一部ご紹介します。
▼開発時
・設計ルールを整える
開発に着手する前に、変数の命名規則やフォルダ構成、コメントの付与方法など、設計ルールを統一しておきます。
これらのルールを事前に整備することで、誰が開発を担当しても一定の品質と認識が保たれ、結果として後続の保守・運用における負担の軽減に繋がります。
引数の名前は概要が分かる文字列、かつ、入出力方向がわかる接頭字(in / out / io)を付加し、ワークフ ロー内で一意とする。
プロジェクトのフォルダ構成を共通化し、どのロボットでも同じ基準で管理できるようにする。
コメントの記載方法を定め、誰が参照しても処理内容を理解しやすい状態にする。
・開発標準フレームワークや共通部品を使う
ゼロから作らずに、あらかじめ用意した部品や標準フレームワーク(一般的には「テンプレート」と呼称される場合が多いです。例:UiPathの場合、RE Frameworkなど)を利用します。よく使われる処理を共通化や、開発の土台を統一することにより、管理やメンテナンスがスムーズになります。またロボットの品質を一定に保ちやすくなります。
すべてのロボット開発の際に標準フレームワークをベースにすることで、エラー時のリトライやログ管理などの仕組みを一から作らずに導入できる。
・シンプルな設計を意識
一つのロボットに多機能を持たせず、分割・部品化して設計します。ある一定のまとまりの処理単位でワークフローを分割し、処理を判別できるよう命名したワークフローファイル名に反しない範囲で処理更新/機能追加を検討します。
・複雑な構造を避ける
条件分岐や繰り返し処理を必要以上に重ねすぎないように、ルールを決めておきます。
また、複数の条件を全てロボット側で制御しようとすると条件分岐や繰り返しなどの制御構造が複雑になる可能性があるため、処理条件をロボットの外部から取得することを前提に処理を設計することも検討します。
処理日が〇月の第○営業日なら処理a、〇月の第○営業日なら処理b、のように複雑に分岐する場合、ワークフローで各パターンの処理判定をするのではなく、判定に必要な情報をインプットファイルやインプットボックスの入力情報、設定ファイル等から取得して処理する。
・固定値を直接書かない (ハードコーディングを避ける)
ロボットの中に固定値(フォルダパスやURLなど)を直接書かず、外部の設定ファイルや変数にまとめておきます。そうすることで、業務や環境が変わっても簡単に修正でき、ロボット本体を作り直す必要がなくなります。
・必要に応じてワークフロー内にコメントを残す
開発者担当者以外の方がロボットを見たときに、理解しづらい複雑な処理には意図を記録しておく。
▼リリース時
・ドキュメントを整備する
設計書や仕様書などのドキュメント類に記載されている内容を実装内容と一致させる。
・ロボット処理で使用するドキュメントの目的がわかるように
処理内でドキュメントの出力や読み込みを行うロボットの場合、どのような目的で使用するかをわかるよう仕様書等に記載しておく。
・レビューと引継ぎを行う
リリース時に関係者向けにレビューを実施し、担当者以外でもロボットについて説明できる状態にします。
▼運用時
・すべてのロボットを一元管理する
稼働中のロボットは必ず管理部門や専任担当が把握し、野良ロボットを防ぎます。
・ドキュメントの内容は常に最新の状態を保つ
ロボットの改修を実施したら、設計書や要件定義書も最新化する。
・利用状況を監視し、未使用のロボットは削除やバックアップフォルダに格納する
RPA管理者は定期的に実行ログやヒアリングでロボットの利用状況を確認し、棚卸しする。
・引継ぎ体制を整える
ロボットの開発/実行担当者が変わるときは十分な引継ぎ期間を設ける。
・改修やメンテナンスの経緯をドキュメントに記録する
ロボット一覧に改修の経緯を記録する。その際、枝番等を使用してロボットのバージョン管理も行い、後からロボットの修正内容を追跡できるようにする。
日付:20××年1月1日
変更者:○○
シナリオ番号:変更前1.1.0 →変更後1.1.1
変更内容:システム画面の○○操作追加に伴う○○処理追加
変更理由:要件変更に伴う修正
影響範囲:後続の保存処理に影響あり
確認状況:テスト済み、本番リリース済み
以上が押さえておきたいポイントです。
必ずしも一度にすべて実践する必要はありません。小さな取り組みを積み重ねていけば、ロボットの複雑化・野良化を招きづらくする強固な開発/運用体制の基盤づくりに繋がります。
それぞれの現場に合った最適解をアップデートし続けることが大切
ここまで開発、リリース、運用の各工程におけるポイントを挙げてきましたが、すべての現場に通用する“万能な解決策”は存在しません。開発標準フレームワーク(例:UiPathの場合、RE Framework)や開発/運用のガイドラインを適用するといったような体制を整えている現場でさえ、複雑なロボットが存在するのが実情です。
事実、様々なお客様に対してRPA開発支援を行っている弊社担当者からは、開発や運用の支援に入る段階で下記のようなロボットの問題を目の当たりにしてきたという声が寄せられました。
・RPAの専用部品で実現できない操作を、一般的でない部品の組み合わせや特殊な手法で実装している
・繰り返しや分岐が何重にも入れ子構造になり、処理が追いにくい
・同じ機能を持つ処理が共通化されておらず、あちこちに重複して記述されている
・コメントが不足しており、必須アウトプットと副次的アウトプットの区別ができない
・画面遷移などの状態変化が処理内容から推測できない
上記を踏まえると、特殊な業務上の事由や複雑な処理を実装しなければならない背景、独自の組織文化といった要因を紐解き、現場の実情に即して柔軟に開発/運用体制を設計することが欠かせません。「汎用的なベストプラクティス」をそのまま取り入れるだけでは対応しきれないケースは少なくないのです。
標準フレームワーク(例:UiPathの場合、RE Framework)や運用ルールのガイドラインを活用することは有効ですが、それだけでは不十分な場合もあるということです。
必要に応じて 専門家による第三者視点の伴走支援を取り入れることも有効です。
ここでいう伴走支援とは、単なる技術的なアドバイスではなく、現場に寄り添いながら課題の整理や改善提案を行い、定着まで一緒に進めていく支援を指します。これにより、自社単独では気づきにくい改善点を客観的に把握し、結果として運用の安定につなげることができます。
まとめ、次の一歩
ロボットの複雑化や野良化は、導入が進んでいる企業ほど直面しやすい“身近な課題”ですが、小さな課題を放置し続けてしまうと、将来、業務全体に致命的な影響を及ぼす可能性があります。まずは現場のロボットの現状を把握し、「どこから改善できるか?」をチームで話し合ってみることも有力な改善の一歩です。
弊社では、野良ロボットの課題解消に向けたご支援はもちろん、RPAに関する様々な課題の解消をサポートしております。より良い体制でRPAを推進していきたい場合や、外部専門家による支援をお考えの場合は、是非一度ご相談くださいませ。
本記事のカテゴリ :RPA技術コラム
PickUP
本記事に関連するCACのサービスやお役立ち情報をご紹介します。
RPA技術レポート無料ダウンロード
- 【コラム】RPAによる業務改善、効率化推進の成功のカギ【連載第二弾】~モデルケース② 最適な業務選定~
- 【コラム】どうもうまくいかない!?SharePoint Online(SPO)とRPAの”あるある”をこう解決した!
- 【コラム】2022年人気コラムランキングを大公開
- 【コラム】S-1から読むUiPathとRPAとシステムアーキテクチャ
- 【サービス】RPA開発/サポートサービス
- 【サービス】RPA+Oneソリューション
- 【サービス】RPA研修 自社開発イネーブルメントプログラム
- 【動画】CAC RPAセミナー オンデマンド
- 【資料ダウンロード】美しいコードをみると感動する、美しいワークフローの作り方|CAC RPA White Paper